赤ちゃんも親もなるべくご機嫌で過ごしたい
赤ちゃんの睡眠に関して、実は産前からたくさん調べて準備してきました。
私は元々本当に寝るのが好きで、「寝かしつけに1時間」「夜泣きで徹夜」という生活ではイライラが止まらない自分が容易に想像できてしまい、なるべくそれを避けたいなと思っていました。息子と笑顔で接するためにも、できることなら寝るのが得意な子になってくれるとうれしいなと。なかなか上手くいかないこともあるだろうけど、できるだけのことはしてみよう!というのが基本スタンスです。
何かを調べる、計画する、実際やってみて調整する、また検証する、という実験みたいなサイクルが性に合っていることもあり、意外と楽しく生活リズム整備に勤しんでいます。
やったことは、大きく分けて2つです。
- 息子の寝室の睡眠環境を整えること
- 家族で生活リズムを整えること
この記事では、息子の寝室の睡眠環境について書いています。
前編となる家族の生活リズムについてはこちらの記事にまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。
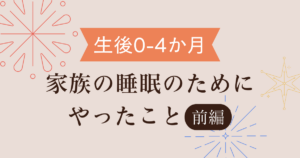
※この記事は専門家の書いた記事ではなく、我が家の息子の成長記録です。お子さまによっても状況によっても千差万別のお悩みがあると思いますが、あくまでどなたかの「参考」になることを祈って公開します
息子の寝室の睡眠環境
我が家では生後3週間から、親子別室で寝ています。退院してすぐは親子同室で寝ていたのですが、私も夫も息子の寝言やちょっとした動きでも目が覚めてしまうタイプで、質の良い睡眠が全く取れない状況が続き精神的に参っていました。夫婦で話し合い、米国小児科学会などの団体も推奨していないことは承知の上で、別室を選択しました。
ちなみに、我が家は両親が遠方で仕事もしており現実的にサポートは頼めない状況なので、基本的に産まれた日からずっと夫と2人で子育てをしています。
結果的に、我が家には親子別室の寝室環境がとても合っていました。
息子は寝室のベビーベッドで、光や音の影響を最小限にぐっすり寝てくれています。私たちは19時すぎに夜の寝かしつけを終えた後はフリータイム。家の間取りにもよるとは思いますが、息子の就寝中過度に気遣うことなく夫婦だけの時間を楽しめるようにしておくことは、産後のストレスを大きく減らしてくれると思います。
息子の睡眠環境としては、主に下記4点を整えました。
- 安全な寝床:ベビーベッド/ベビーモニター
- 適切な湿度:温度設定機能付き加湿器
- 適切な温度:スリーピングバッグ
- 遮光:遮光フィルム
- 遮音:ホワイトノイズ
赤ちゃんの心地よい環境というのは大人と少し違っているのですが、息子の部屋をつくったことで息子のためだけに環境を整えることができました。例えば、赤ちゃんにとってちょうどよい20℃くらいの室温は、大人にはちょっと寒いです。ほかにも、遮光で睡眠の質は上がると思うのですが、夫婦の寝室は東向きなので朝は自然光で起きたい、とか。当たり前といえば当たり前ですが、赤ちゃんと親でニーズの違いがあるんですよね。
安全な寝床:ベビーベッド
息子のベビーベッドはレギュラーサイズ(120×70cm)で床板が高いものを使っています。
我が家は夫婦共に平均よりも背が高いので、腰を守るためにハイシートタイプを選んでよかったです。赤ちゃんの体重はどんどん増えていくので、少しでも負担の少ない環境をつくっておくことが健康維持につながると思います。
つかまり立ちをするまでは、ベッドの下部が収納として使えます。初めの頃は突然物が増えてしまう場所を確保するのも大変なので、ある程度まとめてベビーベッドの下にしまっておけるのはとても便利です。おむつなどの消耗品のストックも、ここに置いています。
ただし、子どもがつかまり立ちをするようになると床板を下にずらす必要があるため、この収納スペースはなくなってしまいます。つかまり立ちまでは半年以上あることが多いと思うので、少しずつベッド以外の収納スペースも整えていくと良いと思います。
ベビーベッドのサイズは120×70cmのレギュラーサイズを使っていますが、生後2か月くらいから寝返りをしなくてもずりずり色々な方向に動いて端から端まで使っていたので、置く場所の制約がない限りはレギュラーサイズを選ぶのが良さそうです。ミニサイズだと想像より早く狭く感じてしまいそう。
ベビーベッドには洗えるベビーマットレスと防水シーツを敷いていて、吐き戻しやおしっこ漏れがあっても基本的には防水シーツだけを洗濯すればOK。もしも守り切れなかった場合はマットレスも洗おうと思っていますが、使用し始めて3か月程度、今のところベビーマットレスを洗う事態にはなっていません。
ちなみに乾燥機可で色味が好みな防水シーツが意外と見つけにくかったのですが、実際に3ヶ月以上洗濯乾燥をして縮みや劣化をほぼ感じていないのでこちらおすすめです。
安全な寝床:ベビーモニター
そして、感謝が止まらないベビーモニター。我が家は小鳥さんのかたちのCubo aiを使っています。
少しお値段は張るのですが、使い始めたら抜け出せない!産後1番見ているアプリはぴよログかベビーモニターかの2択というほど使用頻度が高いので、コスパはとても良いと思います。
Cubo aiはスマホに接続してモニターを見るタイプ。夫やベビーシッターさんに息子を任せて家を出ている時も、ベビーベッドで寝ている姿を見て安心することができます。スマホではモニター表示を小さくして他のアプリを使いながら動画を表示させておくこともできるので、実は今もこの文章を書きながら上部にモニターを表示させてお昼寝を見守っています。
また、赤ちゃんの睡眠環境を整えるときに便利な温度湿度計とホワイトノイズを流す機能も付いているので、この機能を別で用意する必要もありません。
さらに、映像録画機能や写真撮影機能もあります。息子は初めての寝返りを夜中2:30にしたのですが、もちろんその瞬間は夫婦共々爆睡しており。朝起きてびっくりして仰向けにしたりしててんやわんやでしたが、寝返りの瞬間は録画で残っていたのでしっかり見ることができました。いつか初めての寝返りの瞬間を大きくなった息子に見せてあげたいと思っています。
ちなみに結構しっかりしたお値段で怯むのですが、私はブラックフライデーと公式ストアのセールの組み合わせで27,000円程度で購入しました。価格がネックで迷っている方は、お時間が許せばセール期間を待ってみると良いかもしれません。
適切な湿度:温度設定機能付き加湿器
加湿器は、産後すぐに買い足しました。
赤ちゃんの睡眠環境には40〜60%の湿度がちょうど良いそうなのですが、元々持っていたスチーム式の加湿器はパワフルすぎてすぐに湿度が上がりすぎてしまうのと、湿度と共に温度も上がってしまうというデメリットがあり。こちらはリビングと夫婦の寝室用にして、息子の寝室用に加湿器を探していました。
購入したDainichiの加湿器は湿度設定が可能で、構造がシンプルなのでお手入れが簡単。湿度下がってないかな?と何度もCuboの湿度表示を確認することなく、安心して息子の眠りを見守れるようになりました。我が家では常に50%の湿度設定で使っており、一日に一度夕方に水を補充しています。
また、フィルターのお手入れは2週間に一度、クエン酸洗浄を行っています。リビング用のスチーム加湿器、ヘルシオウォーターオーブンも同様に定期的なクエン酸洗浄が推奨されているので、2週間に1度お手入れするのをルーティンにしています。
加湿器の前面に現在の湿度が表示される仕様なのですが、光が気になる場合表示を消すことができます。遮光を徹底したい場合には、「チャイルドロック」と「お手入れリセット」ボタンをピッピッと鳴るまで同時長押しすればOK。上面のランプは消せないため、我が家ではマスキング遮光テープを上から貼り付けています。
適切な温度:スリーピングバッグ
冬季の息子の部屋は暖房なしで17-22℃。赤ちゃんの快適な睡眠時の温度は、20℃前後と言われています。
このため、我が家の室温であれば着るもので調整できる範囲と判断して、暖房なしで過ごしています。退院してからずっと息子が使っている、エルゴポーチのスリーピングバッグにはTOG(Thermal Overall Grade)という寝具用品の断熱性や保温性を表す数字が付いていて、この室温ならだいたいこのくらいの服装で寝るのが心地よい、というのが分かりやすいチャートも用意されています。
冬季、17-18℃まで室温が下がりそうなタイミングでは2.5TOGのスリーピングバッグと長袖の肌着、それよりも暖かい時には1.0TOGのスリーピングバッグと長袖の肌着、というのを基本に、1枚足したりしながら温度調節をしています。
寝返り前までの約3か月間は、手を身体の前にぎゅっと寄せるコクーンスワドルバッグというスリーピングバッグを着て寝ていました。
新生児から4か月頃まではモロー反射が強い時期と言われていて、せっかく寝ることができても自分の手や足の動きで起きてしまうことが多いため、手を押さえてあげると安眠につながるとのこと。これは息子を見ていても本当にその通りだなと思っています。気持ちよーく寝ていても、突然ビクビクっと身体が動いて自分の手が顔に当たって驚いて起きてしまったりして、可愛いんですが何度もだと本人も親も疲れます。
息子は最初の頃、おくるみも併用していました。(お昼寝はおくるみ、夜の就寝はエルゴポーチ)
着るものを変えることで昼夜の区別をつけるにも役立つかなと考えたのと、エルゴポーチを昼の間に洗いたかったので、使い分けをしていました。同じようにモロー反射を抑えられるのですが、おくるみだと激しい動きに耐えられず徐々にはだけてしまうんですよね。息子は結構ダイナミックに手足を動かすタイプだったので、よく手がニョキっと出てきていました。
このため、手足がバタバタして寝付けてないな…と思うことが増えた生後1か月半頃からは、昼夜どちらもコクーンスワドルバッグで寝るようにしました。
公式サイトに「寝返りの兆候が出てきたら腕出しをする」と記載があります。息子は3か月で初めて寝返りをしたため、腕出しをはじめました。実はあまりそれらしい兆候がなく突然の初寝返りだったのですが、コクーンスワドルバッグはボタンを外せばすぐに腕出しすることができたので助かりました。
また、寝返り後は手を身体の前に寄せる必要はなくなるのですが、動きが激しくなって足がベビーベッドの柵にひっかかることがあるそうです。息子もかなり動きが激しく、夜間はベビーベッド内を縦横無尽に動き回りながら寝ているので、コクーンスワドルバッグ卒業後は同じエルゴポーチのジャージースリーピングバッグを使っています。ジャージースリーピングバッグはコクーンスワドルバッグと同様に足の部分が寝袋のように覆われているので、赤ちゃんの足がベビーベッドの柵に引っかかるのを防いでくれます。着心地はコクーンスワドルバッグと同じだと思うので、睡眠環境をなるべく変えないまま寝返りに対応することができました。
遮光:遮光フィルム
寝室の遮光は初め、カーテンで行っていました。ただ、息子が5時や6時など早めに起きることがあり、我が家は起床を7時に整えていきたかったのでフィルムを使って遮光を強化することにしました。
遮光フィルムは一度貼ると基本的には貼ったままなので、息子の部屋では当面つけっぱなしの予定です。窓を綺麗に拭き上げた上で、スプレーで窓に水を吹きかけてフィルムと窓ガラスを密着させて使用します。この時に、ある程度フィルムに厚みがあってシワになりにくいと綺麗に仕上がりやすいです。接着剤を使うわけではないので、フィルムを外したい場合は簡単に外すこともできます。
フィルムの窓側は、窓の外から見た時に直接見える面になります。真っ黒だと熱を吸収しすぎてしまうので、この面がホワイトだと良いなと思って探しており、最終的に厚みや室内側の質感も好みだったこちらの商品を選びました。
結果、息子の寝室はほぼ真っ暗に保つことができるようになり、窓の見た目もなかなか綺麗に仕上がりました。カーテンなしというのもさみしいのでIKEAのお手頃な遮光カーテンを付けていますが、窓からの光は昼夜問わず全く気になりません。換気のために朝窓を開ける際、フィルムとの干渉はなくスムーズです。
夜中に部屋に入ると加湿器のランプが少しぼやぁっと明るく見える気がします(前述の通り、遮光テープは貼っています)が、今のところ息子の睡眠に影響ないためそのままにしています。
フィルムの貼り方に関しては綺麗に仕上がるコツを掴んだので、貼り方解説記事を作成しました。これから設置される方、よかったら参考にしてください。
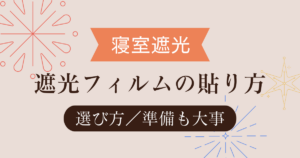
遮音:ホワイトノイズ
遮音についてはとっても簡易なのですが、ベビーモニターで紹介したCubo aiを使ってホワイトノイズを流しています。これを忘れると少し大きな生活音を出してしまった時に反応して起きてしまうことがあるので、息子が寝ている間は基本的にずっと流しっぱなしです。
ホワイトノイズの音量は50dB程度が良いとのことですが、我が家では35dBほどで十分そうだったのでこの大きさで流しています。音量は音量測定webさんやスマホアプリなど無料で簡単に測れるツールがたくさんありました。何種類か試してみると安心できると思います。
親子別室かつホワイトノイズを流しているおかげで、リビングで何も気遣うことなく普通に過ごしていても大丈夫です。特に夜の寝かしつけ後の19時半以降はごはんを食べたりテレビを見たり何かと大きい音が出がちですが、ストレスなく過ごすことができてとてもありがたいです。
家族の睡眠が整う=家族の気持ちが整う
家族の睡眠を整うにつれて、産後少し不安定になっていた気持ちも整っていくのを感じています。
赤ちゃんがしっかり眠れないと「どうしてだろう?」と理由を考えてしまうのが親心で、私も実際に息子と生活する中で何度も理由を考えましたし、本やネットでいろんな情報を読み漁りました。
ただ情報をインプットするだけだけでなく、自分の家や家族に合わせるにはどうすれば良さそうか考えたり、自分の好きなデザインのものを探したりすること、それを夫とも共有して一緒に考え実践すること。これを通して、課題と真っ向から向き合うことができ、上手くいった時はとてもうれしく、親としても一歩前に進めたような気がしました。
今後も息子の睡眠にはいろんな変化があると思うので、その変化に戸惑ったり驚いたりしながらも、変化と向き合うことを楽しみながら過ごしていければいいなと思っています。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
この記事では息子の寝室の睡眠環境について書きましたが、前編となる家族の生活リズムについてもよろしければご覧ください。
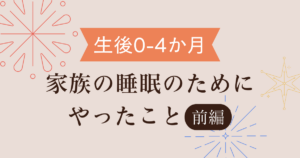
【月齢毎】データで育児ログ
この記事では離乳食をはじめるまでの低月齢時の睡眠について、基本的な考え方を書いてきましたが、各月齢のより詳細なスケジュールや実際のデータはこちらにまとめています。
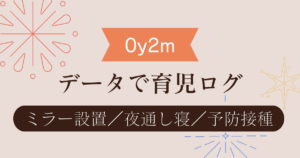
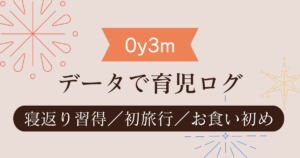
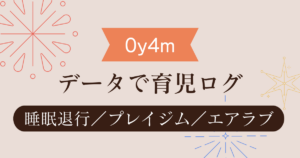

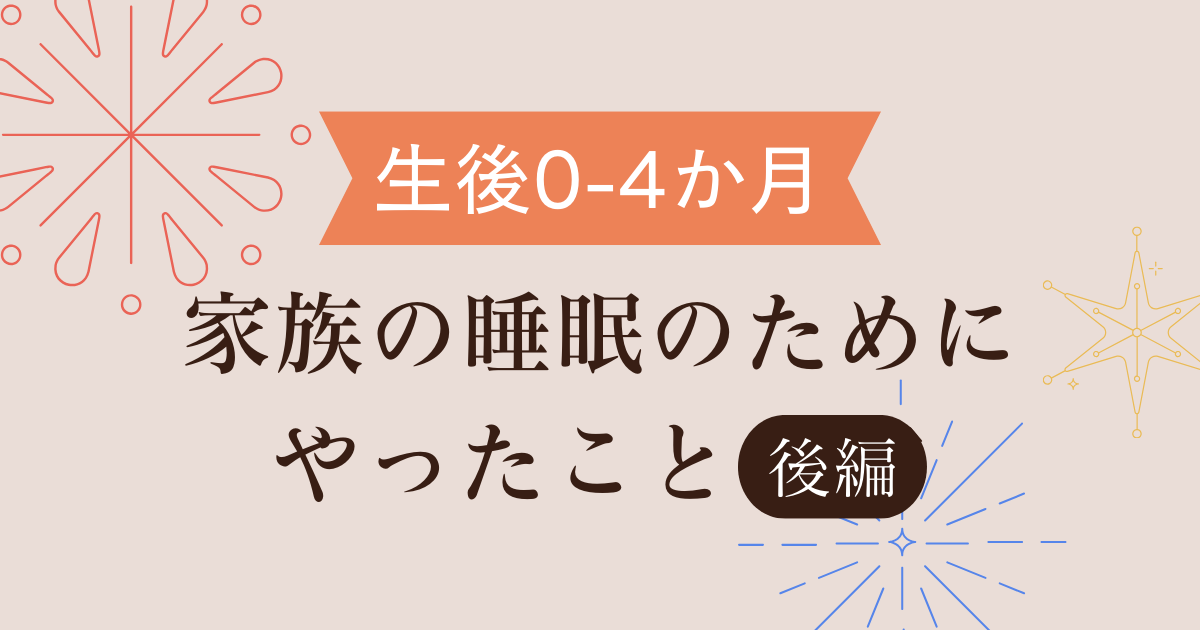







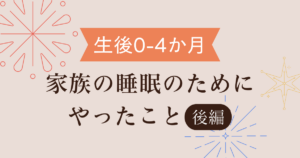
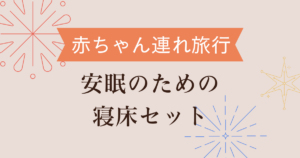
コメント